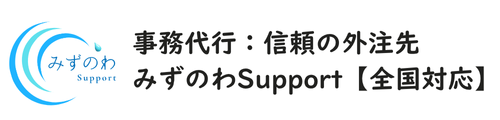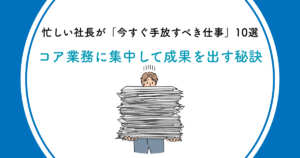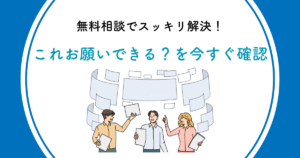事務作業の属人化はなぜ危険?マニュアル化と事務代行のすすめ
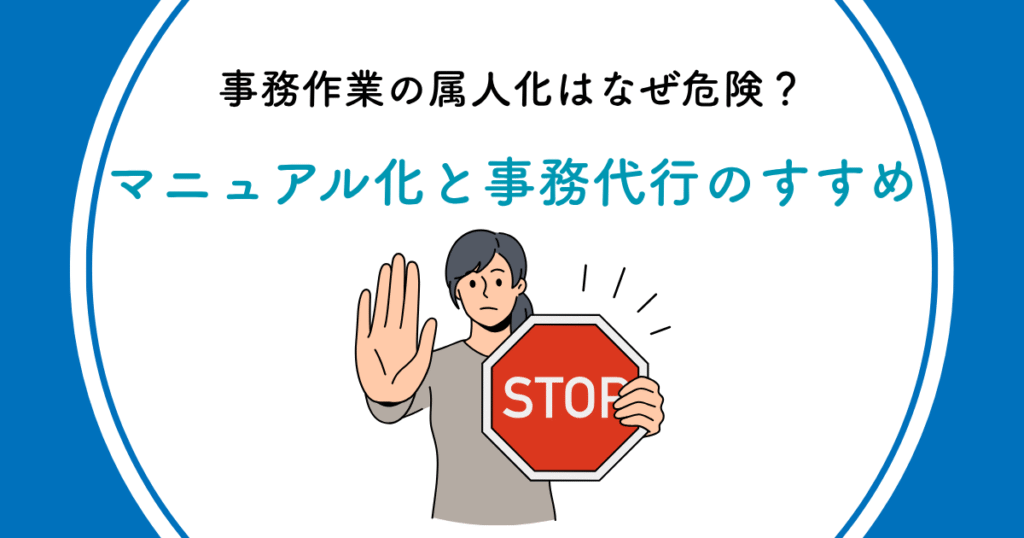
「これは○○さんにしかわからない」「担当が休んだだけで業務が止まった」
そんな属人化のトラブル、あなたの会社でも起きていませんか?
小さな組織ほど「なんとなく誰かがやっている」状態が放置されがちですが、実はそれこそが大きなリスクの種。
今回は、業務の属人化がなぜ危険なのか、そしてそれを解決するためのマニュアル整備と事務代行活用について、具体的に解説します。
なぜ「属人化」は中小企業のリスクになるのか
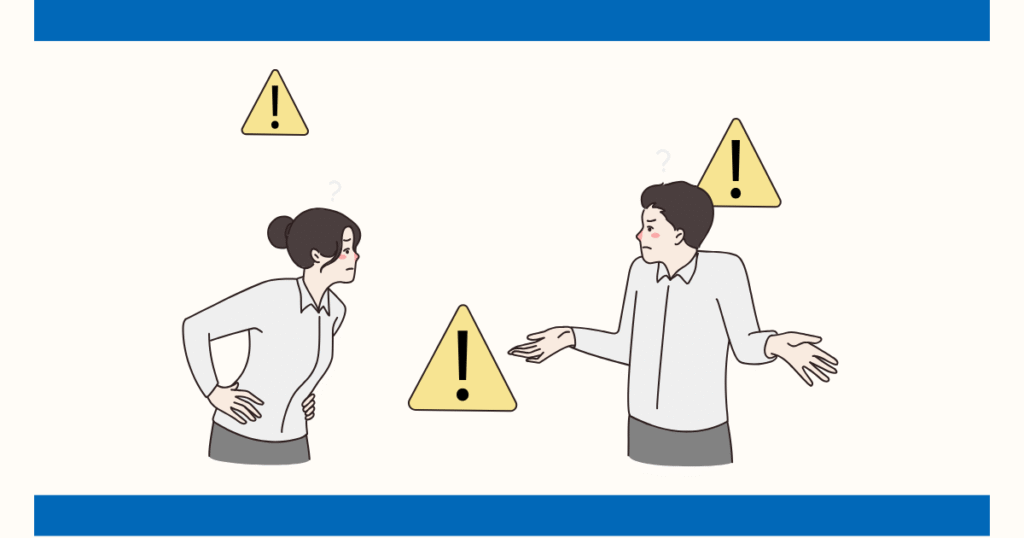
業務の属人化──つまり、特定の人にしかわからない仕事が社内に存在している状態。
これは一見、スムーズに回っているように見えて、実は組織運営上の大きなリスクです。
担当者がいないと仕事が止まる
誰がやっているのか分からない、担当者が休んだら進まない。
そんな経験、ありませんか?
属人化が進むと、「○○さんがいないと回らない」という状態が常態化します。
小さなミスやトラブルならまだしも、大切な取引先への対応や請求業務などが止まってしまうと、信用問題にも直結しかねません。
「人」ではなく「仕組み」で業務を回せる体制づくりが必要なのです。
情報やノウハウが社内に残らない
属人化された業務の多くは、その人の頭の中や手元にしか情報がありません。
たとえば「この帳票はいつ誰にどう送る」「こういうミスはここを見れば分かる」といった“暗黙知”が典型です。
もしその担当者が急に不在になったら、残された人は“どこから手をつければいいのか”さえ分からない。
これは情報資産の損失でもあります。
記録や手順が整っていなければ、同じ品質・同じスピードで仕事を引き継ぐことは難しくなります。
人材の退職が大きな痛手に
特に中小企業では、少人数で幅広い業務をこなすことが一般的。
1人の退職が、業務全体に及ぼすインパクトは想像以上に大きいものです。
「いなくなって初めて分かった」では遅いのです。
業務の属人化が進んでいる状態は、言い換えれば「退職=システムダウン」になる危険性をはらんでいます。
事務作業のブラックボックス化を防ぐことは、企業としての安定性を保つためにも非常に重要な取り組みです。
マニュアル化が生む、3つの好循環
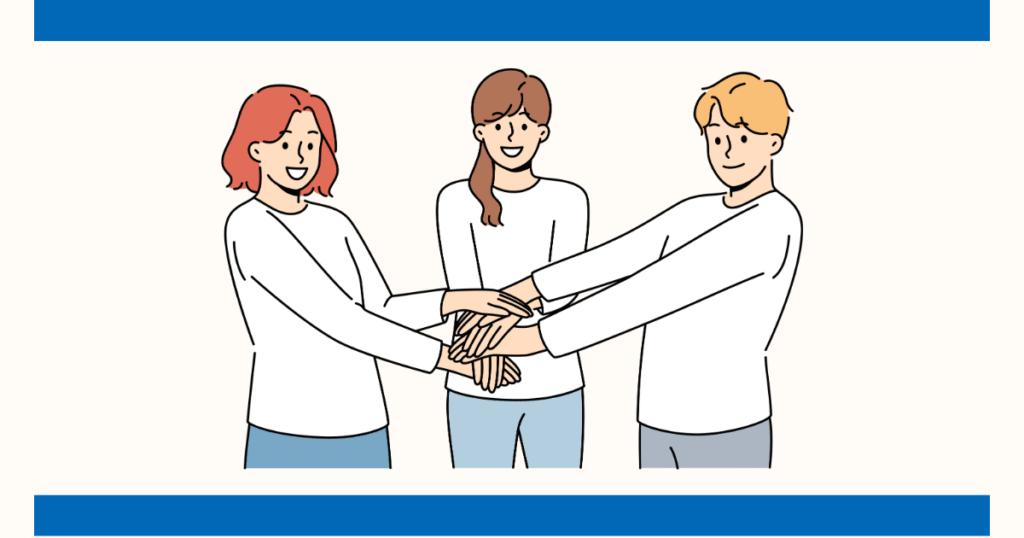
属人化を防ぐために、まず取り組みたいのが「マニュアル化」です。
ただの手順書と思われがちですが、実はマニュアルは業務の可視化・平準化・効率化を同時に進められる強力なツールです。
引き継ぎがスムーズになる
誰かが休んでも、マニュアルさえあればすぐに対応できる。
これが一番のメリットです。
急な休職や退職、繁忙期のサポートなど、イレギュラーな事態でも「とりあえず読めばできる」状態にしておくことで、業務の停滞を防げます。
特に事務作業は細かな手順が多く、人に聞かなければ分からないこともたくさんあります。
だからこそ、マニュアルで“言語化”することがカギなのです。
業務の見直し・効率化ができる
マニュアルを作る過程は、実は「業務を整理する機会」でもあります。
「この作業、本当に必要?」「この順番、変えた方が早くない?」といった気づきが、思わぬ改善につながることも。
普段は流れ作業になっているルーチン業務も、文字に起こしてみるとムダや重複が見えてきます。
結果として、効率的な手順へとアップデートされ、全体の作業時間が削減されるケースも少なくありません。
属人化からチーム化へつながる
属人化は「○○さんだけが分かる状態」。
一方で、マニュアル化された業務は「誰でも対応できる状態」。
つまり、情報が“個人のもの”から“チームの共有財産”に変わるのです。
これは社内コミュニケーションにも好影響を与えます。
「自分のやり方」が可視化されることで、他のメンバーとの連携もしやすくなり、業務の質とスピードが自然と底上げされていきます。
事務代行を選ぶメリットとは?
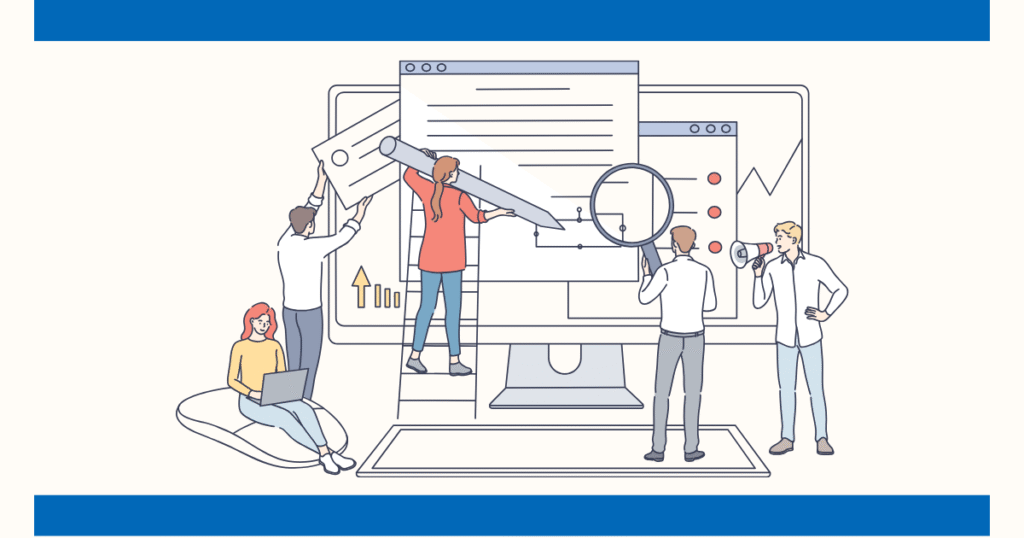
「人手が足りない」「でも採用コストもかけられない」──そんなときの選択肢として注目されているのが、オンラインの事務代行です。
業務の一部を切り出して任せることで、社内の負担を減らしながら、生産性を上げることができます。
業務の標準化と分担が自然に進む
事務代行に依頼するには、「何を」「どのように」お願いするかを明確にする必要があります。
つまり、委託するために“業務を整える”機会が生まれるということ。
結果として、社内で曖昧だった業務の流れやルールが整理され、他のメンバーでも対応できる“標準化”が進みます。
また、「社内はこの部分、事務代行はこの部分」と分担しやすくなるため、属人化対策にもつながります。
社内にないスキルや視点が入る
事務代行の多くは、複数社で経験を積んだプロの事務スタッフ。
たとえば「Googleスプレッドシートで関数を組んで効率化」「Googleドライブでデータを整理」「請求業務のチェック体制を提案」など、
自社では思いつかなかった方法を提示してくれるケースもあります。
この“外の視点”が、日々の業務改善やミス防止のきっかけになることも多く、社内にない知見を取り入れる意味でも有効です。
「いざという時」のリスク分散になる
人手不足や急な退職、業務量の波に備えるためにも、事務代行は“セーフティネット”の役割を果たします。
常時フル稼働で依頼しなくても、「必要なときに必要な分だけ」頼める柔軟性があるのもメリット。
社内リソースだけでギリギリ回すのではなく、「外部に頼れる体制がある」というだけで、精神的にも経営的にも余裕が生まれます。
マニュアル×事務代行で“強いチーム”をつくる
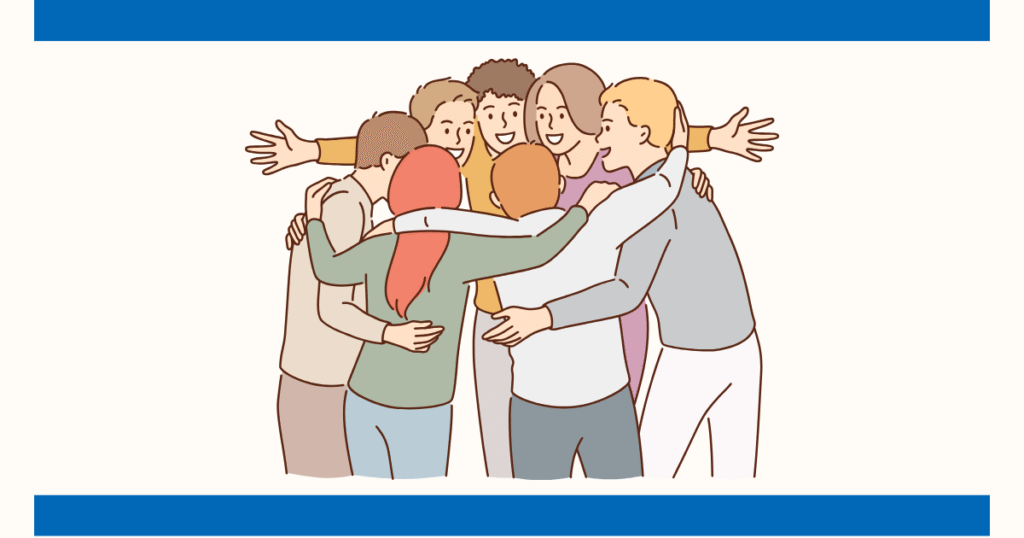
属人化を防ぎたいなら、マニュアル化と事務代行の“合わせ技”が効果的です。
この2つを組み合わせることで、業務が標準化され、誰でも対応できる柔軟な体制が整います。
すぐに始められる!マニュアル整備の第一歩
いきなり完璧なマニュアルを作ろうとする必要はありません。
まずは「やっていることを順番にメモする」だけでも十分です。
たとえば──
- 「〇〇のファイルを開いて」「△△を確認して」などの操作手順
- 対応のタイミングや頻度
- 送付先や確認ポイント など
作業中に自分がやっていることを“実況中継”する感覚で記録すれば、自然と業務の見える化が進みます。
委託前に押さえておきたいポイント
事務代行に依頼する際は、次の3点を意識しておくとスムーズです。
- 業務の範囲と優先順位を明確にする
- 使用するツールやデータ共有方法を決めておく
- 「不明点があればいつでも聞いてOK」のスタンスをとる
この準備ができていれば、委託先は迷いなく対応でき、ミスや確認の手間も減らせます。
実際に委託されている業務の例
「どこまでお願いできるの?」という疑問も多いはず。
以下のような業務は、事務代行でよく依頼される範囲です。
- 請求書の発行・管理
- 勤怠データや交通費の集計
- メールの振り分け・テンプレート対応
- 社内資料やマニュアルの整形
- 面接の日程調整や応募者対応
- チャットのログ整理や月次レポート作成
共通するのは、“オンラインで完結できる事務作業”という点。
自社で抱え込むよりも、ルール化して手放すことで、業務の安定と余裕が生まれます。
まとめ|属人化リスクに備え、柔軟で強い業務体制を

中小企業における事務作業の属人化は、業務停滞・情報の分断・退職時の混乱といったリスクを引き起こします。
この課題に対する有効な対策が、業務のマニュアル化と事務代行の活用です。
マニュアル化によって業務が可視化・標準化され、属人化を防げるだけでなく、チーム全体のスピードと連携力も向上。
さらに、事務代行を併用することで、負荷分散・スキル補完・緊急時対応といった外部リソースの強みも取り込めます。
「人」で回すのではなく「仕組み」で回す体制は、社内の安定だけでなく、経営の柔軟性にもつながります。
属人化に不安を感じたら、まずは1つの業務からでも、手放してみることをおすすめします。
みずのわSupportでは、1人社長〜30名規模ほどの法人さまを中心に、バックオフィス業務のサポートを行っています。
ご相談内容を確認のうえ、3営業日以内にご返信いたします。
受付時間:9:00〜17:00[土・日・祝日除く]
「何から頼んでいいかわからない」「とりあえず話だけ聞いてほしい」という段階でも構いません。
ご希望の業務内容や気になる点を、フォームにご記入のうえ送信してください。